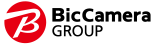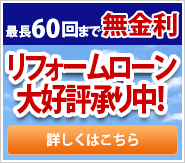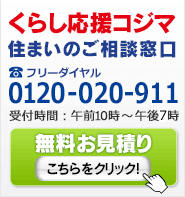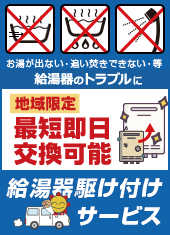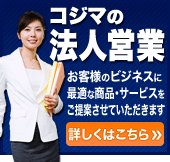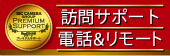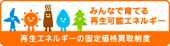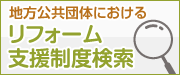経糸について
経糸には綿糸と麻糸があり、麻糸の方が綿糸よりも丈夫です。
また、その組み合わせも綿糸のみのものから、綿と麻を組み合わせたもの、麻糸のみのものまであり、当然麻糸を使ったものの方が丈夫です。
経糸が丈夫であれば、それだけ多くのいぐさを織り込む(打ち込むという)ことが出来るので、目の詰まった丈夫な畳表を織ることができ、かつ表面にきれいな山型が作られて厚みが増すために、足あたりや肌触りといった感触もよくなってきます。
いぐさの効果
いぐさの内部はスポンジ状で、無数の穴があり、その穴に空気中の二酸化窒素などの有害物質を吸着する性質があります。さらにはアンモニアなどの嫌な臭いも消してくれるなど、空気の浄化作用があります。
産地の違い
最近では安価な中国産の畳表を使うケースが非常に多くなっております。
しかし、国産と比べ以下のような難点が挙げられます。
- 国産に比べいぐさの収穫時期が約1ヵ月早いため、いぐさが未成熟である。
そのため、いぐさの表皮が柔らかく、脆い。 - いぐさを乾燥させる過程で、国産が低温・長時間でじっくり行うのに対し、中国産は輸入の際にコンテナに積むので、虫やカビが発生するのを防ごうと、高温・短時間で行う。そのため、いぐさが乾燥しすぎて水分がほとんど残らず、表皮はカサカサに毛羽立ち、いぐさ本来の粘りや弾力性も失われてしまう。
- 国産と違い、草の選別が農家単位で行われないために、いぐさの品質が均一ではなく、色味もばらつきがある。
そのため、化学染料で染色加工をすることが多く、出荷後に色落ちして服などに付着したり、焼けた場合、ムラだらけになり見映えが非常に悪くなる。
最近は、以前に比べると技術や品質も上がってきましたが、まだまだ国産品の出来には及ばないようです。
畳のサイズについて
| 畳の呼び名 | 1畳の大きさ | 使われている地域 |
|---|---|---|
|
・京間(きょうま) ・本間(ほんま) ・本間間(ほんけんま) |
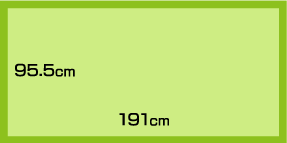 |
京都、関西地方 中国、九州地方 |
|
・中京間(ちゅうきょうま) ・三六間(さぶろくま) |
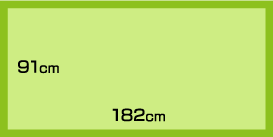 |
愛知、岐阜、三重、福島、山形、岩手、北陸地方の一部、奄美大島 |
|
・江戸間(えどま) ・五八間(ごはちま) ・関東間(かんとうま) |
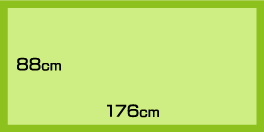 |
関東、東北、北海道、東日本の大部分、全国的な標準規格 |
|
・団地間(だんちま) ・五六間(ごろくま) |
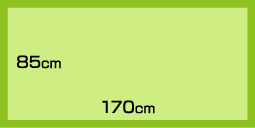 |
公団住宅、アパート、マンション |